「 妖怪 ハヤクネロ」
「ハヤクゥ〜ネロ、ハヤクゥ〜 ネロォ〜 」 少し前、我が家の近所には「 妖怪 ハヤクネロ」が現れた。 直接見た者はないが、その姿は全身真っ黒で暗闇では目が赤く光るという。 ラーメンを作る屋台の車に乗って夜9時頃に現れる。ひずんだ笛の音が遠くから近づいてきたと思うと、夜、寝な...
2017年3月31日


オタクか?プロか? ターニングポイントは『入力と出力のバランス』
現在高校二年生の娘が、今、ある大手劇団にどっぷりはまっていて、寝ても冷めてもミュージカル三昧! 部活のため、何ヶ月先のチケット購入ができないので、学校が休みの日は当日券を求めて朝から並んで観劇。さらには新作CDを購入したりyou-tubeの動画や、舞台のDVDを借りてきて日...
2017年3月20日


【育児あるある】子どもの習い事の決め方
「三つ子の魂百まで」と昔の人はよく言ったもので、 3歳までは親の愛情をたっぷりと浴び、3歳を過ぎたら専門家の指導を受ける。そうすると、子どもの才能はプロの領域まで伸びると聞きました。 我が家の娘は少し遅く6歳からバレエを習わせましたが、...
2017年3月17日


【室内DIY】勝手に閉まる手作り自動ドア!
我が家の子どもがまだ小さかった15年位前、 「エアコンをつけているから扉を閉めてー!」 と言ってもできる訳はないので、DIYデ自動ドアを考案しました。 電気代節約&子育ての小さなイライラ解消になりますよ! 【 材 料 】 テグス(半透明の丈夫な糸)、 フック画びょう、...
2017年3月16日
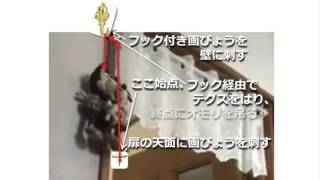
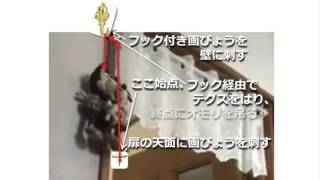
「幼稚園に入ったらす〜ぐに高校生になるわよぉ!」
「幼稚園に入ったらすぐに高校生になるわよ!」 幼稚園入園の時に、先輩ママに言われた言葉が今でも忘れられません。 子育てをしていると日々実感するのですが、赤ちゃんはあっという間に子どもになります。そして、小学生はあっという間にニキビ面になります。...
2017年3月14日


